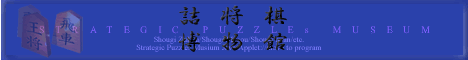詰将棋の草創(江戸初期)
現存する最古の詰将棋は、慶長7年(1602年)に出版された初代大橋宗桂(1555-1634)の『象戯作物』である。初代宗桂は、碁の本因坊算砂とともに碁将棋の専門家として、信長・秀吉・家康に仕えた人物。もって時代を知ることができよう。 将棋の遊びそのものは古くからあり、碁に古くから詰碁があり、象棋(中国将棋)にも残局(詰将棋)が古くからあることから考察すると、詰将棋ももっと古くからあったのかも知れないが、一応、現存する最古の詰将棋の作者、初代宗桂を「詰将棋の元祖」とすべきであろう。 初代宗桂の作品は「詰将棋の原型」というべきもので、形式も内容も至って原始的なものである。彼の作品は、門人などの終盤の力を養成する練習問題だったらしく、指将棋の終盤と似ており、謎解きとしてはあまり面白いものではない。駒の配置は未洗練で、妙手も少ない。現代では、詰上りに手駒の余る作品は「不完全作品」とされ、詰将棋の資格がないが、彼の作品には「手余り」が多く見られる。詰将棋の約束は、まだ今日のように厳密でなかったのである。 しかし、彼の作品には余詰はなく、詰将棋の基本的な約束は今日と変りがない。詰将棋の理念は彼によって確立されたと見るべきであろう。 また重要なことは、彼が「詰将棋献上」の先例を作ったことである。すなわち、彼の『象戯作物』(五十番本)は、彼が将棋所(幕府の官制で、将棋衆を統括する役。厳密には「名人」と違うが、実際はほぼ同義)に就任したのを記念して出版し、徳川幕府に献上されたもので、後の将棋家元はこの前例に倣い、名人就任が内定すると詰将棋百局集を出版し、幕府に献上するようになった。この伝統のため、江戸時代の歴代将棋家元は熱心に詰将棋を創作し、これが主流となって詰将棋はいちじるしく発達したのである。 初代宗桂の跡を継いだ二代大橋宗古(二世名人。初代宗桂の子。1576-1654)は、寛永十三年(1635年)に詰将棋百番『象戯図式』(俗称『将棋智実』)を出版、献上した。しかし、これは初代宗桂の遺作を増補したもので、宗古のオリジナルではないらしい。作品の内容も『力草』と大して変りがない。 二代宗古の子、三代大橋宗桂(1613-1660)は、棋力が七段に止まったため、幕府に詰将棋献上はしなかったが、献上に備えて詰将棋を創作していたらしく、正保三年(1646年)に『象戯作物』(俗称『将棋衆妙』)を刊行している。彼の作品も「手余り」を認めているので「草創期」型の作品であるが、内容はかなりすぐれていて、現代でも通用するような巧妙な作品も多く、初代宗桂や二代宗古に比べて技術進歩の跡が見られる。詰将棋は単なる「練習問題」から、だんだん興味深い「謎解き」に進化し、詰将棋らしい風格を備えてきたのである。 詰手数について見ると、初代宗桂の作品は平均約18手であるが、二代宗古になると約23手、三代宗桂は約25手とだんだん長くなり、この面からも創作技術の進歩の跡がうかがわれる。 なお草創期には、大橋家以外の棋士や民間人も詰将棋を作ったと思われるが、それらは全く遺っていない。大橋家三代の作品三百題が草創期の遺産のすべてである。
詰将棋の興隆(江戸前期)江戸初期に誕生した詰将棋は詰将棋献上の慣例のために、将棋家元の作品を中心に進化を続けた。 草創期の作品が妙手に乏しかったり、手駒が余ったりして味気なかったのに比べ、次の時代になると巧妙な狙いを持った作品が誕生し、「手余り」作品は姿を消した。草創期の作品は、ただ頭を悩ませるだけで面白味の乏しいものが少くなかったが、時代とともにこういった作品は少なくなり、詰将棋は興味深い「謎解きパズル」に成長した。実戦では絶対に見られぬ奇抜な妙手が珍重され、巧妙な狙いを持つ難解作が誕生した。 詰将棋近代化の父と言えるのは初代伊藤宗看(三世名人。1618―1694)である。彼の作品『象戯図式』(俗称『将棋駒競』慶安2年。1649年刊)には「手余り」作品がなくなり、今日でも通用する詰将棋のスタイルが確立した。(ただし、「玉方最長」のルールは厳密でなかったが、これは古図式全般に言えることで、これが喧しく言われるようになったのはごく最近のことである。) 初代宗看の作品は、内容に深味があり、変化が幅広く、難解なのが特徴である。詰手数は平均22手で、三代宗桂の25手に比べてかえって短くなっているが、無意味な手順が切り詰められ、短い手順の中に妙手が濃縮され、変化手順の中にも妙手があるのが新しい特徴である。「難解性」は詰将棋評価の重要な要素であるが、この点でも大きな進歩が認められる。『駒競』の作品は従来の作品に比べて巧妙であり、難解である。 四世名人五代大橋宗桂(初代宗看の子。1636―1713)の『象戯図式』(俗称『象戯手鑑』、寛文9年刊)も『駒競』と同様に重厚な作品であるが、一部の作品に創作遊戯的要素が認められ始めたのが注目される。例えば「双方飛車不成」「双方角不成」「龍追い廻し」「桂追い作品」「持駒一揃い作品」など、鑑賞向きの作品が誕生している。 歴代家元の献上図式を鑑賞すると、彼等が面目にかけて秀れた作品を作ろう、先覚の業績を凌ごうと努力した跡がうかがえて興味深い。この新工夫の現れが「遊戯的作品の誕生」だったのである。 六世名人三代大橋宗与(1648―1728)は、次に述べる二代伊藤宗印の後で名人になった人であるが、作風から便宜上ここで述べておく。彼の献上図式『象戯作物』(俗称『将棋養真図式』、享保元年。1716年刊)も、作風は初代宗看や五代宗桂と軌を一にするものであるが、技法上新しい進歩は見られない。宗与は創作力が低く、無責任な門人にでも代作させたためか、従来作品の改作(盗作)や不完全作が多く見られ、献上図式史上の一大汚点となっている。 初代宗看から三代宗与までの作品について共通して言えるのは、棋型が実戦型から少しずつ崩れ始めており、詰手数の割合に使用駒数が多く、配置が広がっており、変化も苦心して仕上げた跡が見られることである。現代作品のようにスマートではないが、時の高段者が心血を注いで創作した跡がうかがわれる。
黄金期の前夜(元禄-享保時代)時代とともに成長してきた家元棋士の詰将棋は、五世名人二代伊藤宗印(生年不明―1723)の登場により飛躍的な展開をする。 五代宗桂までの作品は、一部遊戯的作品があるにせよ、大部分が重厚な実戦型作品だったのに対し、宗印の詰将棋は実戦型とは縁もゆかりもない「創作型」の作品である。彼の作品は二百題あり、元禄十三年(1700年)献上された『象戯図式』(俗称『将棋勇略』)は、全題、玉を中段(4―8段目)に配置した創作型詰将棋で、詰手順も捨駒の粋を尽くした軽妙なものである。自陣玉(1―3段玉)が全くないのは古今を通じて異類の作品集である。これだけの手腕がある作者なので、自陣玉の作品集が別にあったのではないかとも想像される。もう一つの作品集『将棋精妙』は、『不成百番』の別名があるように、どの作品にも不成の手筋が入った作品集で、巻末の二題は玉方の角不成と飛不成の伏線で終局不詰となる「逃れ図式」となっている。なお、この『将棋精妙』は作者生存中は出版されず、書稿のままで伝えられたらしく、幕末の安政五年(1858年)になって初めて出版されている。 この宗印の二つの作品集は、当時までの詰将棋の理念から飛躍した奇抜なもので、宗印の並々ならぬ手腕と感覚を見ることができる。ところで、このように伝統を脱却し、当時としては奇嬌とさえ言える作風に宗印を走らせた動機は何だったのであろうか。 先に述べた通り、歴代将棋家元の献上図式は、彼等の面目にかけても先覚の業跡を凌ぐべく、絶えず工夫改良が行なわれている。ところで重厚を極めた五代宗桂の『象戯手鑑』の存在は、次代の宗印にとって相当な脅威だったと思われる。五代宗桂と同じ次元に立っては『象戯手鑑』を上廻る作品を作ることは不可能に近い。この苦悩と判断が、宗印をして実戦型への訣別、奇嬌な新作風への転換を余儀なくさせたのではないかと考えられる。しかしこの自由な新作風への転換が次代の傑作『将棋無双』や『将棋図巧』を生むキッカケになっていることを考えると、このことは実に大きな意義あることと言わねばならない。 ところで、二代宗印の作品は実は代作ではないか、という疑惑があるので触れておきたい。それは、『将棋勇略』は宗印自身の創作でなく、曲詰集『象戯秘曲集』の作者・添田宗太夫七段が代作したのではないか、というのである。その根拠は、『将棋勇略』が献上されて6年後、宝永3年(1706年)に出版された洗濯周詠編『象戯洗濯作物集』の中に、『将棋勇略』の作品が2題、添田宗太夫作として掲載されているからである。時代や作風や前後の事情から考えると、添田の代作は考えられぬことではない。添田が『勇略』の真の作者とすると、詰将棋の歴史は大切な所でちょっと変ってくることになるが、ともに重要な人物なので言及しておく次第である。 宗印を頂点とする家元棋士の詰将棋は、このようにめざましく発達したが、同時に、詰将棋の面白さは、民間人の関心を呼び起さずにはおかなかった。世は元禄時代、遊興好きの江戸市民にこの面白い詰将棋が流行らぬはずがなかった。 元禄のころから家元棋士以外の詰将棋書が出版され始め、これに多くの民間人の作品が収録されている。これら民間人の棋書を列挙すると次のようである。 1 青木善兵衛編『近来象戯記大全』(元禄8年。1695年) 上のうち『手段草』と『秘曲集』以外の作品は、ほとんどが草創期風の素朴な作品で、取るに足りないものであるが、小原大介、望月勘解由(仙閣)、田代市左衛門などは、遊興的な洒落た作品を何題か残しており、この時代の作品としては注目に値する。 宗印の『勇略』におくれること24年、享保9年(1724年)に出版された伊野辺看斎の『象戯手段草』は、宗印の作品と同様、自由闊達なすぐれた感覚の作品集で、「飛先飛歩」「銀鋸」「四桂詰」「四銀詰」など注目に値する作品を含んでいる。玉の盤面81格全位置配置をはじめて達成したことも記録に値する。『将棋無双』や『将棋図巧』を見た後では地味な印象はやむを得ないとしても、『手段草』は『無双』や『図巧』に先がけて誕生したもので、歴史的意義は高く評価せねばならない。 添田宗太夫の『象戯秘曲集』は、「あぶり出し曲詰」のみを集めた曲詰集で、時代的に見て珍重すべき存在である。なお、本書の刊行は宝暦2年(1752年)で、三代宗看の『将棋無双』より遅いが、添田の活躍期間から、創作は『無双』に先がけて、元禄―享保年間に行なわれていたものと推定される。 こうして、詰将棋は時代の進行とともに発達して、自由な創作型詰将棋が誕生し、技巧的・遊戯的作品が創作されるようになり、三代宗看と看寿の傑作誕生を迎える背景は静かに熟していたのである。 『将棋無双』と『将棋図巧』(享保―宝暦時代)江戸時代の詰将棋の水準は、享保―宝暦時代を迎え、七世名人三代伊藤宗看(1706―1761)と贈名人伊藤看寿(1719―1760)の天才兄弟の出現により頂点に達する。三代宗看は指将棋でも歴代の家元名人中最右翼に位する名人で、その献上図式『象戯作物』(俗称『将棋無双』、享保19年。1734年刊)は『詰むや詰まざるや百番』と呼ばれる古今最高の難解な作品集であり、看寿の献上図式『象棋図式』(別名『象棋百番奇巧図式』・俗称『将棋図巧』、宝暦5年。1755年刊)は「神局」と呼ばれる古今の最傑作である。 『将棋無双』は難解なばかりでなく、構想も技巧もそれまでの作品とは比べものにならぬぐらい卓越しており、妙手、伏線、趣向、遠駒などの技法や長手数記録などあらゆる点で新境地をひらいた。 『将棋図巧』は『無双』にもまさる高度な技巧的作品で、長手数作品や遊戯的作品、構想型作品に高雅な技法が見られる。有名な「六百十一手詰」や「煙詰」、第一番の「角送り詰」など、どれをとっても人間業と思えぬ、人智の限りを尽くした作品である。 この両書は古今を通じて詰将棋の双璧と言われるが、両者を比較すると『図巧』の技巧に一日の長がある。しかし、公平な評価をするには創作された順番も考慮すべきであろう。同時代ではあるが、『無双』の方が幾分先に創作されたであろうから。 なぜこのような傑作がこの時代に生まれたかというと、それは詰将棋献上の伝統と世襲の家元制度と彼等天才兄弟の出現に帰すべきであろう。重厚難解な詰将棋を尊ぶ伝統と、将棋を天職とし、献上詰将棋の創作を神聖な仕事として取りくんだ彼等両天才の研鑚により、奇跡的な作品が誕生したのである。 詰将棋黄金期の諸作品(享保―天明時代)『将棋無双』と『将棋図巧』は同時代の作家に大きな影響を与えずにはおかなかった。両書に刺激されて、続々とレベルの高い作品集が誕生した。その中で最高の作家は数学者久留島喜内である。 久留島喜内(義太)は三代宗看や看寿と同時代の人である。彼は和算史に残る大家で、将棋はアマチュア(四段)であった。彼の作品は『将棋妙案』と『橘仙貼璧』の二書が伝わっているが、ともに刊行年代不明の本で、没後出版ではないか(久留島は宝暦7年、1757年没)と推定されている。久留島の詰将棋には、いかにも数学者らしい閃きがあり、特に遊戯的な趣向詰にすぐれた才能が見られる。有名な「金智恵の輪」「銀智恵の輪」は彼の代表作で、看寿や宗看さえ気付かなかった理論的構想が見事に盤上に展開されている。彼は数学者らしく、一つの法則(構想)を立てると、幾つもの作品に展開している。連作「智恵の輪」はその典型的な例である。彼は棋力が低かったためか、難解作は少いが、趣向詰のアイデアの豊富さは並ぶ者がなく、古今独特の存在である。 三代宗看の弟で看寿の兄に当る八代大橋宗桂(前名伊藤宗寿。1715―1774)は準名人(八段)で終ったが、明和2年(1765年)『象戯図式』(俗称『将棋大綱』)を献上している。八代宗桂は三代宗看や看寿の兄弟だけあってかなりの手腕を有し、作風は『図巧』や『無双』と軌を一にするものであるが、両天才に比べると腕前が見劣りするのはやむを得ない。また、彼は詰将棋の検討力が低かったらしく、不完全作が多いのが惜しまれる点である。 八世名人九代大橋宗桂(八代宗桂の実子。1744―1799)の『象戯図式』(俗称『将棋舞玉』、天明6年、1786年刊)は、献上図式の伝統の最後を飾る作品集で、趣向詰に秀れた手腕を見ることができる。『将棋舞玉』は、内容からいっても献上図式中最も近代的な作品集で、趣向の豊富さでは久留島に次ぐ存在である。一部宗看や看寿の構想の類似作があるが、全体としては献上図式の伝統に恥じぬ秀れた作品集であり、古図式史上重要な位置を占める傑作である。 この時代を飾る異色の作家として、十代将軍徳川家治が挙げられる。家治の将棋好きは有名で、詰将棋百番『御撰象棊攷格』を著した。『攷格』は天明ごろの作品集と推定され、作品は取るに足りぬものが多いが、徳川将軍が詰将棋を作ったことは奇談と言えよう。これも宗看や看寿の影響で、詰将棋が熱狂的に流行したことを示すものであろう。 詰将棋衰退期(幕末-明治大正時代)三代宗看・看寿の出現で絶頂に達した詰将棋は、やがて衰退期を迎える。そのキッカケは詰将棋献上の廃止である。 九世名人に就位した大橋宗英(1756―1809)は、「詰将棋は充分発達した。これからは指将棋を発達させよう」と唱え、みずから詰将棋の献上を止めてしまった。彼の言葉は看寿・宗看に及ばぬことを悟ったための逃げ口上でもあり、一つの見識でもあった。詰将棋を一題も作らなかった彼は、人に理由を聞かれて「詰将棋なら桑原君仲にでもできるではないか」と答えたという。真偽は判らないが有名な伝説である。彼以後の将棋家元も、彼にならって「詰将棋蔑視」を唱え続けたので、詰将棋は急速に衰退した。 桑原君仲はこの衰退期における第一人者である。桑原は九代宗桂の弟子(四段)で、『象棋奇正図』(寛政4年(1792年)刊。天保7年(1836年)『将棋玉図』として復刻)と『将棋極妙』(嘉永2年。1849年刊)の合計二百番の詰将棋を創作して、家元の無気力を尻目にひとり気を吐いた。彼の詰将棋は軽妙な作品が多く、特に曲詰の創作に工夫が見られるが、看寿・宗看のような独創性とスケールの大きさはない。 桑原は専門家とアマチュアの中間的存在だったらしいが、彼以後の詰将棋は棋士の手を離れ、比較的棋カの低いアマチュア愛好家の手に移っていった。幕末から明治大正時代にかけての主な作品集としては、和中氏『象戯童翫集』(文政11年。1828年)、河村古僊『将棋貫珠』(明治10年。1877年)、松本朋雅翁『将棋万象』(明治38年。1905年)、高橋与三郎『将棋真田』(大正14年。1925年)等があるが、いずれも内容は程度の高いものではない。 明治大正時代に入っても専門棋士は詰将棋を顧みなかった。棋士は将棋で生活をせねばならず、詰将棋の報酬では食えなかったからである。このころから新しい傾向として、新聞雑誌などのマスコミに詰将棋が掲載されるようになったが、専門棋士の名で発表された作品は、ほとんどが啓蒙を主体としたごく程度の低い作品か、または古作を盗用したもので、見るべきものは乏しい。 詰将棋の復活(昭和初期―現代)昭和に入って、詰将棋は活発な息吹きをとり戻し始めた。その動機はアマチュア将棋雑誌『将棋月報』の誕生と天才作家酒井桂史の登場である。酒井は主として昭和初期の『将棋月報』に本格的作品を発表し、一躍詰将棋の第一人者となった。彼の作品は看寿や宗看に似た華麗難解なもので、詰将棋復活を示唆するものであった。 彼に刺激されて、数多くのアマチュア作家が誕生し、『将棋月報』に作品を発表した。最初は素人の将棋同好会誌的な雑誌であった『将棋月報』は次第に詰将棋専門誌の観を呈するに至り、同誌を舞台にして詰将棋の創作活動が活発に行なわれるようになった。『将棋月報』の活動は終戦の直前まで続いた。このころ活躍した主な作家としては酒井以外に、今田政一、丸山正為、塚田銀波(正夫)、杉本兼秋、里見義周、田辺重信、滝谷正郷、岩木錦太郎、小林豊、有馬康晴、岡田秋葭、 北村研一などが挙げられる。一方、戦前の新聞や大衆雑誌を中心とする専門棋士による作品の流れは明治大正期そのままであったが、 塚田正夫(後の贈十段)を中心に清新な短篇詰将棋が誕生したことは特筆に値する。 時代は戦後に移り、『将棋月報』の同人たちは新しく発足した『詰将棋パラダイス』に集まり、さらに多くの詰将棋愛好家が増え、詰将棋の創作活動は一層活発になった。現代の詰将棋はほとんど専門棋士の手を離れ、『詰将棋パラダイス』『近代将棋』(廃刊)『風ぐるま』(廃刊)『詰棋界』(廃刊)などの将棋雑誌を舞台としたアマチュア作家のものとなっている。現代の作品は重厚さでは古図式に及ばないが、知的で洗練されているのが新しい特徴である。 現代作品の底流は二つに分けられる。一つは看寿・宗看の流れを汲む本格派の創作活動で、多くのすぐれたアマチュア作家の登場により、看寿や宗看にもできなかったような作品も続々と誕生している。もう 一つは、専門棋士の名で新聞雑誌に発表される大衆向けの実戦型詰将棋で、毎月発表される作品の数は膨大なものとなっている。江戸時代に発展し、一度は衰退した詰将棋であるが、現代はルネッサンス期にあると言えよう。毎年発表される作品の質の高さと量から言えば、享保宝暦時代以上であり、現代こそ詰将棋黄金時代なのである。 |
![]()
![]()
Since:20th.December.1999
All right reserved copyright (C) k-oohasi 1999-2019
![]()